
「難しそう」と感じている方必見!
ブラインドの操作方法お教えします[プリーツスクリーン・ハニカムスクリーン編]
ブラインドにはたくさんの種類があり、それぞれの特性に合わせた操作方式が用意されています。それゆえ、「ブラインドの操作って難しそう」と感じてしまう方もいらっしゃるそうです。
そこで、今回はブラインドメーカーのニチベイがプリーツスクリーンとハニカムスクリーンの操作方法についてわかりやすく解説していきます!
プリーツスクリーン・ハニカムスクリーンとは?
見た目は似ているプリーツスクリーンとハニカムスクリーン。まずは、それぞれどのような窓まわりアイテムなのか見ていきましょう。
和モダン空間といえば “プリーツスクリーン”

ジャバラ状の生地を伸ばしたり、折りたたんだりして調光・昇降をするプリーツスクリーン。水平ラインが均等に並んだ意匠は、水平垂直を意識して造られている和室と相性抜群です。
不織布をラインアップしているところも、和室に選ばれる理由のひとつ。和紙の伝統製法を用いてつくられた不織布は、外からの光を受けると生地の濃淡が浮き上がり美しさを放ちます。
デザイン性に優れているだけでなく、光の量や外からの視線を細やかに調節できるのがプリーツスクリーンの魅力です。
暮らしやすさを追求するなら“ハニカムスクリーン”

ハニカムスクリーンは蜂の巣状のセルが縦に連なる立体構造のスクリーンです。省エネ性能は窓まわりアイテムの中でNo.1。蜂の巣状のセルが空気層となり、高い断熱効果を発揮します。窓から入ってくる夏の暑い陽射しと冬の冷気を防ぎ、一年中快適な室温をキープします。 生地が二重になっているため、光を採り入れつつ外からの視線もしっかりガード。まさに、暮らしやすさをアップしてくれる窓まわりアイテムです。
ライフスタイルに合わせて3つのスタイルから選べる
プリーツスクリーンとハニカムスクリーンには、窓の場所やライフスタイルに合わせられるように3種類のスタイルがあります。
1シングルスタイル

1枚の生地からなるシングルスタイル。シンプルな構造で、生地の意匠を活かしたスタイリングが楽しめます。生地を上げると室内が丸見えになるので、あまり頻繁に開けない窓や外からの視線が気にならない窓に適しています。
2ツインスタイル

プリーツスクリーンの中で最も人気があるツインスタイル。透け感の異なる生地を上下に配置しており、中間バーの上下で生地の配分を調節し調光します。
光だけでなく、視線のコントロールも得意。上部に不透明生地・下部にシースルー生地を指定すれば高い建物からの視線を、生地の配置を逆に指定すれば通行人の視線を遮ることができます。
3アップダウンスタイル

アップダウンスタイルは雪見障子やカフェカーテンのように、上部と下部から通気や採光が行えます。とくに、インテリア上級者に人気がある仕様です。外からの視線は気になるけれど、庭や空を眺めたい、風を室内に採り入れたい方に最適です。
プリーツ&ハニカムの操作方式をご紹介
プリーツスクリーンとハニカムスクリーンは異なるアイテムですが、生地を折りたたんだり伸ばしたりする構造が一緒なので、共通の操作方式が採用されています。
ここからは、それぞれの操作方式の特徴や適応スタイル、おすすめの窓についてご紹介します。
シンプルな意匠で建築士にも人気のコード式

コードを引いてスクリーンを上げ下げするコード式。ヘッドボックスがコンパクトで、窓枠に設置してもあまり目立たないことから、建築士さんにも好まれる操作方式です。
構造がシンプルゆえに、操作荷重がダイレクトに伝わります。スピーディーに操作できる反面、大きいサイズや重量のある生地だと操作が負担に感じてしまうおそれも。コード式を選ぶ際は、窓の大きさを考慮しましょう。
シングルスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
コードを下に引き下げます - スクリーンを下げるとき:
コードを下に少し引いて手を緩めます
ツインスタイル・アップダウンスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
昇降側(左右どちらか指定可能)のコードを下に引き下げます - スクリーンを下げるとき:
昇降側のコードを下に少し引いて手を緩めます - 調光するとき:
(昇降とは反対側)のコードを下に少し引いて手を緩めるとスクリーンが下がり、コードを下に引き下げると、スクリーンが上がります
シングルスタイル、ツインスタイル、アップダウンスタイル
小窓、スリット窓、腰高窓
ベーシックな仕様のチェーン式

ベーシックな仕様のチェーン式。1本のチェーンでスクリーンを上げ下げします。昇降をアシストする機構が備わっており、大きなサイズの窓でも比較的軽い力で操作可能です。
小窓や腰高窓だと窓よりもチェーンが長くなってしまうことがあります。見た目が気になる方は、あらかじめ操作チェーンの長さを短めにオーダーしましょう。
- スクリーンを上げるとき:
手前のチェーンを下に引き下げます - スクリーンを下げるとき:
手前のチェーンを少し引いて手を緩めると、ゆっくりと自動で下降します
掃き出し窓、大開口窓
シングルスタイル
1本のチェーンで昇降と調光ができるワンチェーン式

ワンチェーン式は1本のチェーンでスクリーンの昇降・調光が行える操作方式です。チェーン式同様、昇降をアシストする機構が備わっており、大きなサイズの窓でも比較的軽い力で操作可能です。
下降時の操作音も静かで、寝室にもお使いいただけます。あえて操作チェーンを長めにオーダーして、ベッドに横たわりながら操作できるようにしている方もいらっしゃいますよ。
- スクリーンを上げるとき:
手前側のチェーンを下に引き下げます - スクリーンを下げるとき:
手前側のチェーンを少し引いて手を緩めると、ゆっくりと自動で下降します - 調光するとき:
奥側のチェーンを少し引いて手を緩めると、中間バーがゆっくりと下がり、奥側のチェーンを引き下げると、中間バーが上がります
掃き出し窓、大開口窓、寝室の窓
ツインスタイル、アップダウンスタイル
安心安全に特化したスマートコード式

スマートコード式は操作部の位置が高く、コードもループ状になっていないため、小さなお子さまやペットがいるご家庭におすすめの操作方式です。チェーン式やワンチェーン式同様、下降ブレーキ・障害停止機構を搭載しており、安心・安全で機能性に優れた操作方式です。 シングルスタイルの場合はボトルプルコードで、ツインスタイルの場合は1本のグリップで、昇降や調光を行います。操作部が小さく、窓辺がすっきりして見えますよ。
シングルスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
ボトルプルコードを繰り返し引きます - スクリーンを下げるとき:
ボトルプルコードを少し引いて手を緩めると、ゆっくりと自動で下降します
ツインスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
切替表示部が「昇降」になっていることを確認し、切替グリップ下のコード止めを繰り返し引きます - スクリーンを下げるとき:
切替表示部が「昇降」になっていることを確認し、切替グリップ下のコード止めを少し引いて手を緩めると、ゆっくりと自動で下降します - 調光するとき:
切替表示部が「調光」になっていることを確認します。切替グリップ下のコード止めを少し引いて手を緩めると、中間バーがゆっくりと下がり、繰り返し引くと中間バーが上がります
※昇降と調光を切り替えるとクリック感があり、目視なしでもスムーズに操作できます

切替グリップを回し昇降と調光を切り替える
掃き出し窓、腰高窓、小窓
シングルスタイル、ツインスタイル
1番操作がかんたんなコードレス式

中間バーやボトムレールについているグリップを動かすだけのコードレス式。最もかんたんな操作で、ブラインドが初めてな方やコードやチェーン操作に苦手意識がある方に向いています。コードやチェーンがぶら下がらず、洗練された雰囲気を演出できます。
コードレス式は、あまり高い窓だと手が届きません。ご自分の手が届く高さの窓に設置しましょう。
シングルスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
グリップを持って上に上げます - スクリーンを下げるとき:
グリップを持って下に下げます
ツインスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
ボトムレールについているグリップを持って上に上げます - スクリーンを下げるとき:
ボトムレールについているグリップを持って下に下げます - 調光するとき:
中間バーについているグリップを上げ下げします
腰高窓、小窓、スリット窓、地窓
シングルスタイル、ツインスタイル
どこからでも操作できる電動式

リモコンや壁面のスイッチで操作する電動式。スマート家電コントローラーと連携させれば、スマートフォンやスマートスピーカーでも操作可能です。もし、スクリーンを下げ忘れて外出してしまっても、遠隔でスクリーンを開け閉めできます。
電動式は窓の近くにコンセントが必要です。設計の段階で検討しておきましょう。
シングルスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
リモコンの▲ボタンを押します - スクリーンを下げるとき:
リモコンの▼ボタンを押します
ツインスタイルの場合
- スクリーンを上げるとき:
リモコンの▲ボタンを押します - スクリーンを下げるとき:
リモコンの▼ボタンを押します - 調光するとき:
リモコンの△ボタンを押すと中間バーが上がり、▽ボタンを押すと中間バーが下がります
大開口窓、連窓、高窓
シングルスタイル、ツインスタイル
まとめ
written by
なるほどブラインド編集部
2023.05.30 公開

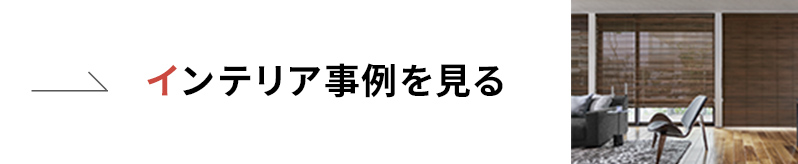
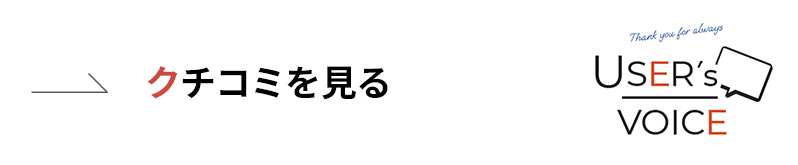
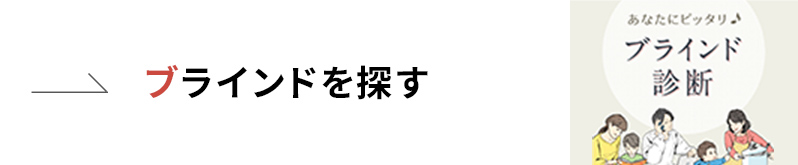


プリーツスクリーンとハニカムスクリーンには、6種類もの操作方式を用意しています。ライフスタイルや窓の場所、家族構成によって使い分けることで、より暮らしやすい空間になります。
生地や色もちろん大切ですが、操作方式もしっかり吟味してくださいね。